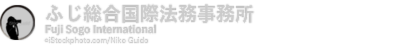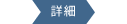ふじ総合法律事務所の「ふじだより」の私の2006年の原稿より。
「日本人の父親に生後認知された婚外子にだけ日本国籍を認めないのは法の下の平等に反し違憲」との今年3月29日の東京地裁での判決は、日本社会での国際的カップルの時代の到来を印象づけている。
このように国籍の違う夫婦や子供の事案は多くあるが、今回のテーマのような国際相続といった事案は比較的まだ少ない。しかし、戦後まもなく米国に移住した夫婦や家族の相続問題に接する機会は増えているし、30年40年後には珍しくない案件になっているように思う。
ある日、セピア色になった写真を携えてある女性が事務所に相談に来た。その写真には軍服を着た白人男性と幼い可愛い少女が写っていた。その女性は、先日のニューヨークで亡くなった米国人を父に持つ日本人女性であった。その後その父親の異母兄弟の代理人弁護士から父の遺産は全て米国にいる子供が相続することになったという通知が来たという。その女性の父親というのは戦後進駐軍として来日し、その折りに自分の母親と知り合い恋に落ち、その女性と日本で婚姻し、彼女が生まれた。その後父親は事情で本国のアメリカに帰ることになるが、彼女の中に日本在住中優しかった父親の記憶が鮮明に残っている。又帰国後もお互いに文通し、自分にとっては大切な父親であった。当然、彼女の戸籍にはその父親の名前が載っている。であるのに、自分を相続人として認めないという米国の弁護士からの説明には納得できるものではないということであった。
ニューヨーク州の相続案件はSurrogate Court(検認裁判所)という特別な裁判所が管轄し、日本の家庭裁判所にあたるFamily Courtは、離婚以外の養子縁組、養育費、幼児虐待等といった家事事件を取り扱い、離婚は日本の地方裁判所にあたるSupreme Court of New York。
このような国際間の相続問題で最初に突き当たる問題が、準拠法の決定である。つまりこの相続問題に日本の国の法律とアメリカの法律どちら国の法律に則り問題を解決するかということである。その適用される法律次第では、相続人の範囲から外れることになったり、相続財産も変わってきたり、又当然、法定相続分や遺留分も違ってくる場合がある。日本の法律では、相続は被相続人の本国法を適用する(法例26条)となっているので、この場合亡くなった父親はアメリカ人であるのでアメリカ法の適用となる。一方、アメリカでは、国としての相続における法律選択の統一した法律はなく、個々に州が独自に制定しているので、ニューヨーク州法(New York Estate, Powers and Trust Law、及びNew York Surrogate’s Court Procedure Act)では、被相続人のDomicile(常居地)[1]、死亡した場所、相続財産の所在地のどれかがニューヨークであればニューヨーク州の法律によって処理されることになる。ニューヨークでは、例えば不動産が州外にある場合には、その不動産がある州の法律を適用することにもなる。これがもし不動産が日本にあるということになれば、基本的に反致(法例29条)により日本法の適用を受けることになる。今回被相続人である父親はニューヨークが常居地であり、ニューヨークで亡くなり、相続財産もニューヨークにあったので、適用法はニューヨーク州法となる。
実はこの父親は遺言を残していた。その中には、米国女性との間に生まれた子供に自身の相続財産を遺贈するとなっていた。そして彼女の名前はそこには載っていなかった。ただ、この遺言は正式なものではなく、証人も付けずに父親が自筆で亡くなる前に家にある便箋に書き殴った類のものであった。その遺言の検認をするために上記の検認裁判所で審理中であった。当然、その遺言の有効性を巡って争うことは可能であり、その遺言の効力が否定されれば、彼女も相続人の1人として法定相続分をもらえることになる。ただ、その遺言の有効性が認められた場合には、ニューヨークでは成人した子供に遺留分を請求する権利はないので、遺言どおりに相続財産は分配されることになる。
その後アメリカの弁護士から送られてきた父親が生前残した遺言のコピーを彼女に見せたところ、その筆跡はまぎれもなく自分が日頃父親から受け取っていた愛情のこもった手紙に書かれていた父の筆跡であり、なによりもその便箋こそが父がいつも使っていたものであるのだという。それを見て彼女は自分の相続分を主張することを止めた。私としては、自分の相続分を主張できる立場にあることは説明した。しかし彼女は、自分は相続財産が欲しくて今回自分の相続が否定されたことに納得いかなかったわけではなく、その父親の子供であったことを自分自身も含めて確認したかったのだという。そして、その愛すべき父親の生前の意思がそうであれば、法的に自分に相続権があったとしてもそれを敢えて争う気はないという。「理屈ではないのですよ。感情で納得できればそれでいいんです。」ということらしい。
[1] あと被相続人のdomicileとよばれ概念は、日本にないので分かりづらいが、住所(residence)とは少し異なり、常居地は社会生活を送る上で中心的な場所であり、基本的に個々人にとって一カ所しかない。